昔のエッセイ/短歌全集 ―アシモフ風に
「かばん」86年2月掲載
ホームページの古いエッセイの中にある文だが、ちょっと読んだら面白かったのでここにも掲載する。
昨年マンションを買い、約千五百万の借金を背負いこんだ。おかげで、一千万という数を、おぼろげながらも実感することができた。だがそれ以上の桁となると、遠い恒星も近い恒星も「お星様」としか見えないように、あいかわらず「大きな数」である。
わが親愛なる夫がパソコン(元祖X1)を買って三年余、彼の努力にもかかわらず、私が覚えたのはスイッチだけだ。
それでも、コンピュータで短歌を作ることは一応考えた。単語等をたくさん入力して組み合わせる方法もあるが、手間がかかりすぎる。それよりも、入力するのは五十音のカナだけにして、三十一文字でできるカナの組み合わせを網羅してしまえば(字余りは考えないものとして)、短歌のすべてを書き切ってしまうことができる、と思い至った。文字通り「短歌全集」である。それがわが家でできるのだ。
さてこの歴史に残る計画を、「ユモレスク」の出版を祝う会(みなさまありがとう) で披露したところ、小森さんが「五十音に濁音や『ぴょ』のようなものを含めると、カナは約百種あり、三十一文字それぞれが百通りだから、100の31乗首になる」と計算してくれた。今野さんが「大変な数ですヨォ」と言うのをモノともせず、「コンピュータだもの、せいぜい親子三代で取り組めば、短歌全集のできあがりヨ」と、大きく出てしまった。わが家のX1かわいさのゆえであった。
そしてそれきり、実際にうちのプリンタが100の31乗首印字するのに何年かかるのか、計算することなく何ヵ月も過ぎてしまった。誰の言葉か忘れたが、真理とは概して無愛想なものであり、こちらから話しかけなければ知らんぷりを決めこんでいるというから、早速計算してみよう。
一年は31,536,000秒。一首印字する時間を4秒と決め、100の31乗は10の62乗におきかえる。式は省略。答えは約12,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000年となる。(もしかして少し違ってたらごめんね) 12.7×10の55乗年と書いた方が良いだろう。
この宇宙が誕生してから現在に至るまでに流れ去った歳月ですら、わずか10の11乗年かその倍ぐらいなのだから… … すごい。
では本にしてみよう。「あ」が31個の第一首ではじまり、「ん」が31個で終るこの全集は、一巻千頁、一頁百首とすると、10の57乗巻の大全集となる(注1)。一巻が1キログラムだったら10の57乗キログラムの紙が要る。どうか爪を噛まないで読んでいただきたいが、これに対して地球の重さ(?) は、ほんの5.983×10の24乗キログラムにすぎない(注2)。
これで私の全集計画はぺしゃんこになってしまったが、無限に等しい数とはいえ、短歌が有限であるという事実は動かせない。短歌は、いわば短歌の女神の巨大な卵巣の中にすべて用意され、順番を待っているのだ。この比喩を続けると、私の場合、著しく「かばん」の品を落とすかもしれないので、残念だがこのへんで話を変えよう。
次に思いついてしまったのが「短歌登録制度」である。
長い長い年月の間には、それと知らずに同じ歌を詠んでしまうケースがあるはずだ。文化的遺産として語り継がれる少数の作品以外は、作品も作者も忘れ去られて、おろかにも再び作りなおされてゆくのではなかろうか。そんな無駄を防ぎ、作者の権利を守るため、短歌をコンピュータに登録しようという提案があっても不思議ではない。
しかし、断っておくが、私はそんな必要も熱意も感じてはいない。それは、同じ作品が生まれる確率の低さ等のケチな、いや数学的な理由ではない。ある種の作品は一度生まれれば、多くの人の精神に効率良く働きかけながら生きながらえるが、忘れられるタイプの作品は、その短い一生で、ほんの数人をなぐさめるだけだ。だから何べんでもチャンスは与えられるべきだと思う。
宇宙的な時の流れの中では、それも自然な現象に見えるが、いかがなものだろう。おや、こんどは足の爪ですか?
原注1 ちなみに俳句は、総句数はたったの10の34乗句、10の29乗巻の全集ですむ。また、こういう全集が完成したあかつきには、カナの列から意味を読みとる作業が、歌人や俳人の仕事となる。
原注2 アシモフのエッセイにそう書いてあったが、その算出方法は、何回読んでもすぐわからなくなる。
昨年マンションを買い、約千五百万の借金を背負いこんだ。おかげで、一千万という数を、おぼろげながらも実感することができた。だがそれ以上の桁となると、遠い恒星も近い恒星も「お星様」としか見えないように、あいかわらず「大きな数」である。
わが親愛なる夫がパソコン(元祖X1)を買って三年余、彼の努力にもかかわらず、私が覚えたのはスイッチだけだ。
それでも、コンピュータで短歌を作ることは一応考えた。単語等をたくさん入力して組み合わせる方法もあるが、手間がかかりすぎる。それよりも、入力するのは五十音のカナだけにして、三十一文字でできるカナの組み合わせを網羅してしまえば(字余りは考えないものとして)、短歌のすべてを書き切ってしまうことができる、と思い至った。文字通り「短歌全集」である。それがわが家でできるのだ。
さてこの歴史に残る計画を、「ユモレスク」の出版を祝う会(みなさまありがとう) で披露したところ、小森さんが「五十音に濁音や『ぴょ』のようなものを含めると、カナは約百種あり、三十一文字それぞれが百通りだから、100の31乗首になる」と計算してくれた。今野さんが「大変な数ですヨォ」と言うのをモノともせず、「コンピュータだもの、せいぜい親子三代で取り組めば、短歌全集のできあがりヨ」と、大きく出てしまった。わが家のX1かわいさのゆえであった。
そしてそれきり、実際にうちのプリンタが100の31乗首印字するのに何年かかるのか、計算することなく何ヵ月も過ぎてしまった。誰の言葉か忘れたが、真理とは概して無愛想なものであり、こちらから話しかけなければ知らんぷりを決めこんでいるというから、早速計算してみよう。
一年は31,536,000秒。一首印字する時間を4秒と決め、100の31乗は10の62乗におきかえる。式は省略。答えは約12,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000年となる。(もしかして少し違ってたらごめんね) 12.7×10の55乗年と書いた方が良いだろう。
この宇宙が誕生してから現在に至るまでに流れ去った歳月ですら、わずか10の11乗年かその倍ぐらいなのだから… … すごい。
では本にしてみよう。「あ」が31個の第一首ではじまり、「ん」が31個で終るこの全集は、一巻千頁、一頁百首とすると、10の57乗巻の大全集となる(注1)。一巻が1キログラムだったら10の57乗キログラムの紙が要る。どうか爪を噛まないで読んでいただきたいが、これに対して地球の重さ(?) は、ほんの5.983×10の24乗キログラムにすぎない(注2)。
これで私の全集計画はぺしゃんこになってしまったが、無限に等しい数とはいえ、短歌が有限であるという事実は動かせない。短歌は、いわば短歌の女神の巨大な卵巣の中にすべて用意され、順番を待っているのだ。この比喩を続けると、私の場合、著しく「かばん」の品を落とすかもしれないので、残念だがこのへんで話を変えよう。
次に思いついてしまったのが「短歌登録制度」である。
長い長い年月の間には、それと知らずに同じ歌を詠んでしまうケースがあるはずだ。文化的遺産として語り継がれる少数の作品以外は、作品も作者も忘れ去られて、おろかにも再び作りなおされてゆくのではなかろうか。そんな無駄を防ぎ、作者の権利を守るため、短歌をコンピュータに登録しようという提案があっても不思議ではない。
しかし、断っておくが、私はそんな必要も熱意も感じてはいない。それは、同じ作品が生まれる確率の低さ等のケチな、いや数学的な理由ではない。ある種の作品は一度生まれれば、多くの人の精神に効率良く働きかけながら生きながらえるが、忘れられるタイプの作品は、その短い一生で、ほんの数人をなぐさめるだけだ。だから何べんでもチャンスは与えられるべきだと思う。
宇宙的な時の流れの中では、それも自然な現象に見えるが、いかがなものだろう。おや、こんどは足の爪ですか?
原注1 ちなみに俳句は、総句数はたったの10の34乗句、10の29乗巻の全集ですむ。また、こういう全集が完成したあかつきには、カナの列から意味を読みとる作業が、歌人や俳人の仕事となる。
原注2 アシモフのエッセイにそう書いてあったが、その算出方法は、何回読んでもすぐわからなくなる。
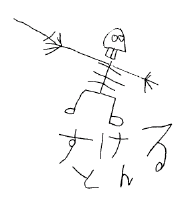
2020年10月追記
冒頭に出てくる借金はぜんぶ返し終わり、離婚し、パソコンはまあまあ得意である。
そして人は変わらないもの。この文体は、何度生まれ変わっても、自分が書いたとわかると思う。
※「すけるとん」のイラストは、どういういきさつか忘れたが、「かばん」誌のこの文章の末尾に添えられていた。 この文章を書いた当事、まだ5歳ぐらいだった長男が書いたものだ。
今は、その子の息子(4歳)がよく遊びに来ている。
